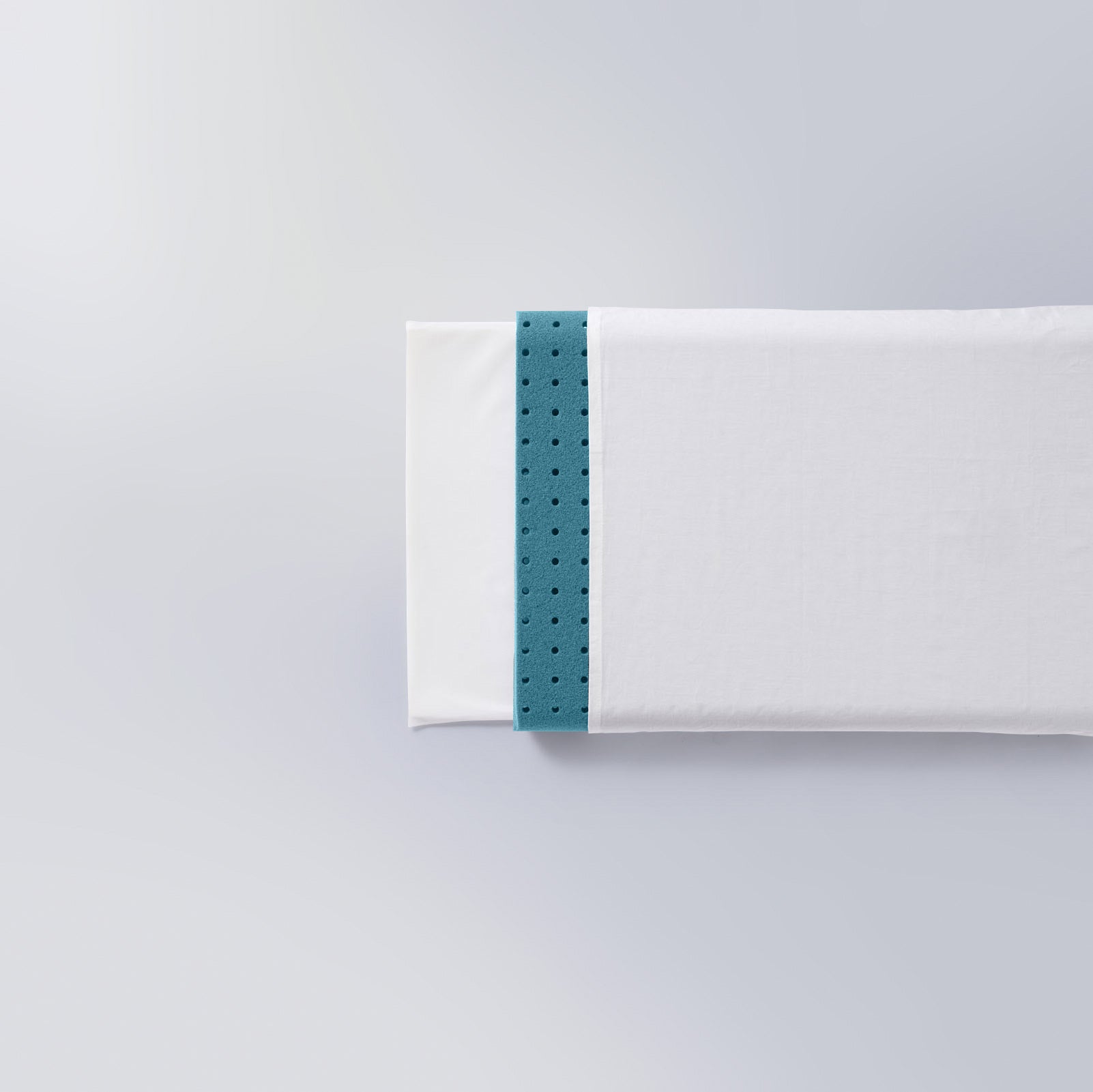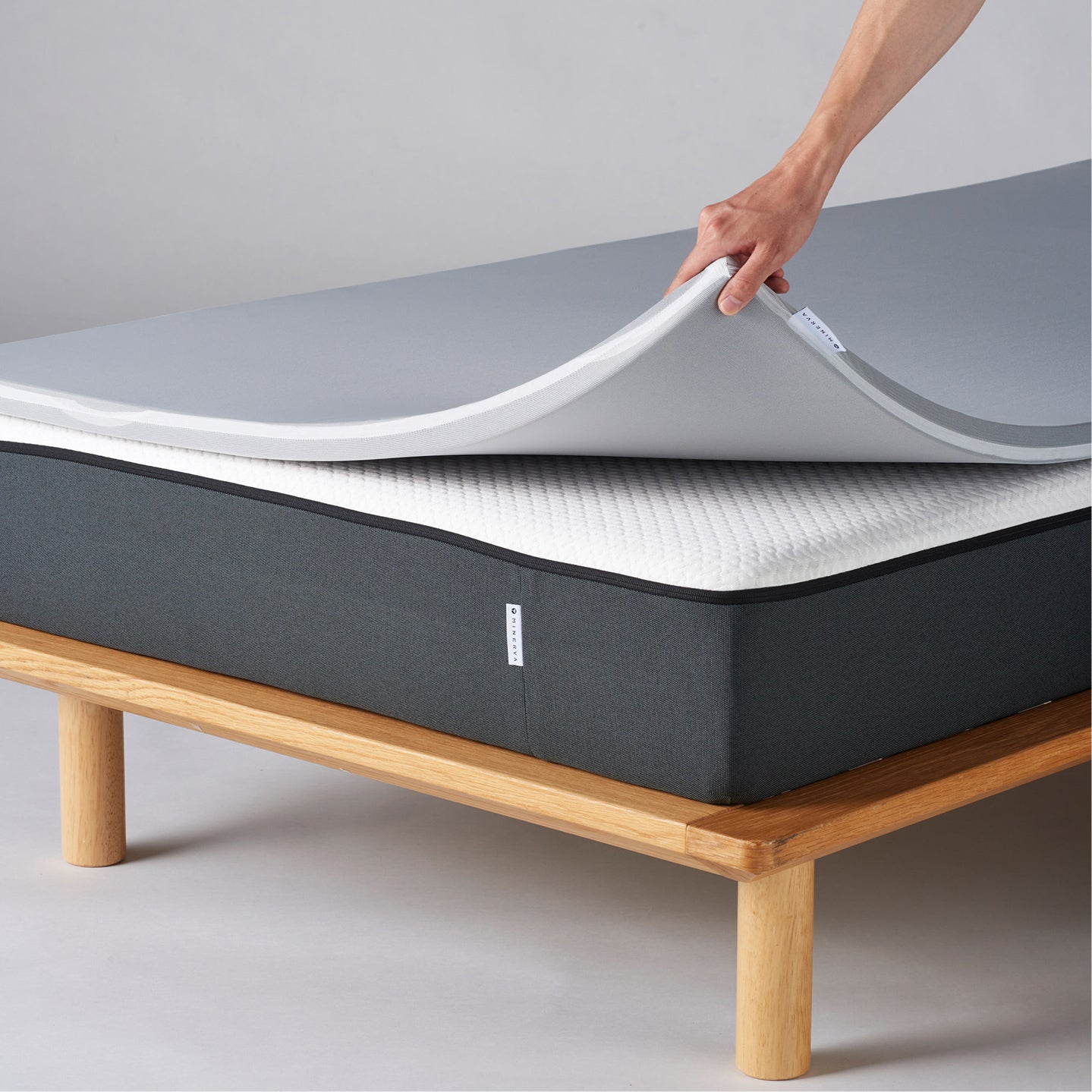マイカート
睡眠不足の解消でだるさ改善とパフォーマンスアップを|「クロノタイプ別」に学ぶ最適な睡眠時間の見つけ方
Share

日中の強い眠気や倦怠感により、仕事のパフォーマンスが上がらず悩んでいる方は多いでしょう。「やらなければならないのに、頭が働かない」という状況は、焦りを生み、さらなるストレスの原因になります。その不調の原因は単なる寝不足ではなく、睡眠の質と日中の行動習慣に隠されている場合がほとんどです。
本記事では、忙しいビジネスパーソンでも実践できる、睡眠不足解消のための具体的な方法を解説します。今日からできる対策を取り入れ、本来の集中力とクリアな思考を取り戻しましょう。
睡眠不足が招く仕事と心身への深刻な影響

睡眠不足は、単に眠いというだけの問題ではありません。脳の機能や自律神経のバランスを崩し、ビジネスパーソンとしての能力を低下させるリスクがあります。
現状を正しく理解し、対策の重要性を再確認しましょう。ここでは、睡眠不足が具体的にどのような悪影響を及ぼすのか、3つの視点で解説します。
脳が機能低下し集中力と判断力を奪う
睡眠が足りないと、脳の前頭葉という部分の機能が低下する傾向があります。前頭葉は、思考や判断、感情のコントロールを司る重要な部位です。
この機能が落ちることは、飲酒時と同程度に判断能力が低下している状態に近いとされています。普段なら数分で終わるメールの返信に時間がかかったり、単純な計算ミスを繰り返したりします。
重要な会議で発言内容がまとまらないのも、脳の処理能力が落ちている証拠です。脳の休息不足は、仕事の質に直結する問題です。
自律神経が乱れて倦怠感とイライラを生む
睡眠不足が続くと、自律神経のバランスが崩れやすくなります。本来、睡眠中は体を休める副交感神経が優位になりますが、睡眠不足の状態では活動モードである交感神経が過剰に働いてしまいます。
その結果、体は常に緊張状態を強いられ、休息できずに疲れが蓄積するのです。また、些細なことでイライラしたり、気分が落ち込んだりといった精神的な不安定さも現れます。
同僚の何気ない一言に過剰反応してしまうなど、職場の人間関係にも悪影響を及ぼすリスクがあります。 心の余裕を取り戻すためにも、自律神経のケアは重要です。
仕事の効率が落ち生産性を低下させる
睡眠不足は、業務効率を低下させる主な要因です。集中力が続かないため、一つのタスクを完了させるのに通常の倍以上の時間がかかってしまうことも珍しくありません。
その結果、残業が増え、帰宅時間が遅くなるという悪循環に陥るでしょう。さらに注意すべき点は、判断力の低下による手戻りの発生です。
修正作業に追われることで、本来やるべきクリエイティブな業務や、将来のための計画立案に時間を割けなくなります。生産性を高めて定時帰宅を実現するためにも、まずは睡眠環境の見直しが重要です。
睡眠不足を招くビジネスパーソンの3大NG習慣

「しっかり寝よう」と意識していても、無意識に行っている習慣が睡眠を妨げているケースがあります。特に現代のビジネスパーソンは、仕事や生活の中で睡眠の質を下げる行動をとりがちです。
これらを避けるだけでも、睡眠の質は大きく改善するでしょう。ここでは、多くの人が陥りやすい3つのNG習慣について解説します。
夜間のブルーライトを浴びる
スマートフォンやパソコンから発せられるブルーライトは、睡眠に悪影響を与えます。ブルーライトは、自然な眠気を促すホルモンであるメラトニンの分泌を抑制してしまいます。夜に強い光を浴びると、脳が「まだ昼間だ」と誤認し、覚醒状態が続いてしまうのです。
特に、ベッドに入ってからのスマホチェックは避けてください。SNSやニュースサイトを見ると、光の刺激だけでなく、情報の刺激によって脳が興奮してしまいます。寝る1時間前にはデジタルデバイスを手放し、脳を休息モードへ切り替える準備をすることが重要です。
寝る直前に食事と飲酒をする
帰宅が遅くなると、どうしても寝る直前に食事をとる機会が増えてしまいます。しかし、胃の中に食べ物が残っている状態で眠ると、体は消化活動を優先するため、脳や体を十分に休めることができません。
結果として睡眠が浅くなり、翌朝の胃もたれや倦怠感につながります。また、寝酒も睡眠の質を下げる大きな要因です。
アルコールは一時的に眠気を誘いますが、時間が経つと分解により交感神経を刺激し、中途覚醒を引き起こしやすくします。食事は就寝の3時間前までに済ませ、アルコールは適量を心がけることが必要です。
15時以降にカフェインを摂取する
仕事中の眠気覚ましにコーヒーやエナジードリンクを飲む方は多いですが、タイミングには注意が必要です。カフェインの覚醒作用は、摂取してから長時間持続するという特徴を持っています。
個人差はあるものの、体内から半減するのに5〜7時間程度かかるといわれています。そのため、夕方以降に摂取すると夜になっても脳が覚醒したままになり、寝つきが悪くなってしまうでしょう。
また、深い睡眠であるノンレム睡眠を妨げる要因にもなりかねません。15時以降は、水や麦茶、ハーブティーなどのノンカフェイン飲料に切り替え、夜の睡眠に備えましょう。
睡眠の質を高める方法5選

睡眠不足を解消するには、単に睡眠時間を延ばすだけでなく、質を高める工夫が必要です。忙しい毎日の中でも取り入れやすく、効果を実感しやすい方法を厳選しました。
自分に合った方法を見つけ、生活習慣に取り入れてみてください。ここでは、今日から実践できる5つの具体的なアクションを紹介します。
自律神経を整えるリラックスタイムの確保する
就寝前の1時間は、意識的にリラックスする時間を設けましょう。おすすめは、38〜40度程度のぬるめのお湯に浸かることです。入浴によって一時的に体温を上げると、その後体温が下がっていく過程で自然な眠気が訪れます。
入浴後は、好きな音楽を聴いたり、軽いストレッチをしたりして過ごすのが効果的です。副交感神経を優位にすることで、スムーズに入眠できる状態を作ります。仕事のことを考えるのは一旦やめ、心身の緊張を解くことに集中してください。
この切り替えが、深い眠りへのきっかけとなります。
朝日を浴びて体内時計をリセットする
良質な睡眠の準備は、実は朝起きた瞬間から始まっています。起床直後に太陽の光を浴びることで、体内時計がリセットされ、正しいリズムが刻まれます。
これは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌予約スイッチを押す行為でもあります。メラトニンは、朝日を浴びてから約14〜16時間後に分泌が増え始めます。
つまり、朝7時に光を浴びれば、夜の21〜23時頃に自然と眠気が来るようになる仕組みです。起きたらまずはカーテンを開け、部屋の中に光を取り込む習慣をつけましょう。曇りの日でも、窓際に行くだけで十分な効果が期待できます。
寝室は寝るだけにする
寝室やベッドの上で、仕事をしたりスマホを見たりするのは止めましょう。人間の脳は場所と行為をセットで記憶する性質があります。ベッドで仕事をすると、脳が「ここは作業をする場所だ」と認識し、無意識に緊張モードに入ってしまいます。
寝室は「眠るためだけの場所」と脳に刷り込むことが重要です。眠くなったらベッドに入り、もし眠れない場合は一度布団から出るのも有効な手段です。
寝具や照明、温度管理にも気を配り、自分が最もリラックスできる環境を作り上げましょう。 環境を整えることが、スムーズな入眠を助けます。
日中に適度な運動を取り入れる
適度な肉体的疲労は、快眠のための重要な要素です。デスクワーク中心の生活では、頭は疲れていても体が疲れていないため、アンバランスな状態になりがちです。日中に体を動かしておくことで、夜になると自然な睡眠圧(眠りたいという欲求)が高まります。
激しい運動をする必要はありません。通勤時に一駅分歩く、エレベーターではなく階段を使う、ランチタイムに散歩をする程度で十分です。
特に就寝直前の激しい運動は交感神経を刺激してしまうため避けてください。夕方までの軽い運動が、夜の深い眠りには効果的です。
睡眠の質を高める食事を意識する
毎日の食事が、睡眠の質に大きく関わっていることをご存じでしょうか。睡眠ホルモンの材料となるトリプトファンという栄養素を意識的に摂取することがおすすめです。トリプトファンは体内では生成できないため、食事から摂る必要があります。
具体的には、大豆製品(納豆、豆腐、味噌)、乳製品、卵、バナナなどに多く含まれています。 特に朝食でタンパク質をしっかり摂ると、日中にセロトニンが作られ、夜にメラトニンへと変化します。
朝の味噌汁や納豆ごはんは、理にかなった快眠メニューです。バランスの良い食事は、日中のパフォーマンス向上にも寄与します。
【クロノタイプ】自分にあった睡眠時間を知る方法

人にはそれぞれ、遺伝的に決まった最適な睡眠リズムがあります。 これをクロノタイプと呼び、自分のタイプを知ることで無理のない生活リズムを作ることができます。
ご自身がどのタイプに当てはまるかを確認し、働き方の参考にしてください。ここでは、代表的な4つの動物タイプに分類して解説します。
日本人に多い「クマ型」の睡眠リズム
全人口の約50%を占めるとされるのが、このクマ型です。太陽の動きに合わせて活動するのが得意で、朝起きて夜眠るという標準的なリズムを持っています。 日中の活動レベルが高く、昼食前後にパフォーマンスのピークを迎える傾向があります。
クマ型の方は、7時間以上の十分な睡眠時間を確保することが重要です。睡眠不足の影響を受けやすいため、規則正しい生活を心がける必要があります。
休日の寝だめは避け、平日と同じ時間に起きることで、体内時計のズレを防ぐことができます。
朝型でエネルギッシュな「ライオン型」の睡眠リズム
人口の15〜20%程度が該当する、いわゆる朝型のタイプです。 早朝から活動することを得意とし、午前中に最も高い集中力を発揮します。一方で、夕方以降はエネルギー切れになりやすく、夜更かしは苦手な傾向があります。
ライオン型の方は、重要な仕事や決断を午前中に済ませるスケジュールが理想的です。夜の付き合いはほどほどにし、早めに就寝することで翌日のパフォーマンスを最大化できます。
無理に夜型の人に合わせようとせず、自分の得意な朝の時間を活用することが成功の鍵です。
夜型で創造的な「オオカミ型」の睡眠リズム
人口の15〜20%程度を占める、典型的な夜型のタイプです。朝起きるのが苦手で、午前中はエンジンがかかりにくい一方、夕方から夜にかけて集中力が高まります。クリエイティブな作業や、一人で没頭する業務に向いている傾向があります。
一般的な始業時間はオオカミ型にとって辛いものですが、可能であればフレックスタイム制などを活用しましょう。午前中は単純作業に充て、重要なタスクを午後に回すなどの工夫も有効です。
夜更かしは得意ですが、睡眠時間が短くなりすぎないよう管理することが必要です。
眠りが浅く敏感な「イルカ型」の睡眠リズム
人口の10%程度とされる、少し特殊なタイプです。睡眠が浅く、物音や光に敏感で、不眠の傾向が見られることもあります。知的好奇心が高く、完璧主義な性格の方に多いとも考えられています。
イルカ型の方は、長時間眠ろうと無理をする必要はありません。「6時間程度眠れれば十分」と割り切り、リラックスする時間を重視しましょう。
寝る前に考え事をしすぎないよう、瞑想や読書などで脳を休める習慣を持つことがおすすめです。短時間でも質の高い休息をとることに意識を向けてください。
まとめ
睡眠不足は、仕事のパフォーマンス低下だけでなく、心身の健康を損なう要因となります。しかし、日々のちょっとした習慣を見直すだけで、睡眠の質は確実に改善できます。まずは、「寝る前のスマホをやめる」「朝食にタンパク質を摂る」など、簡単にできることから始めてみてください。
自分のクロノタイプを理解し、無理のないリズムを作ることも重要です。良質な睡眠は、明日への効果的な投資です。今夜から睡眠環境を整え、すっきりとした朝と充実したビジネスライフを手に入れましょう。
Share