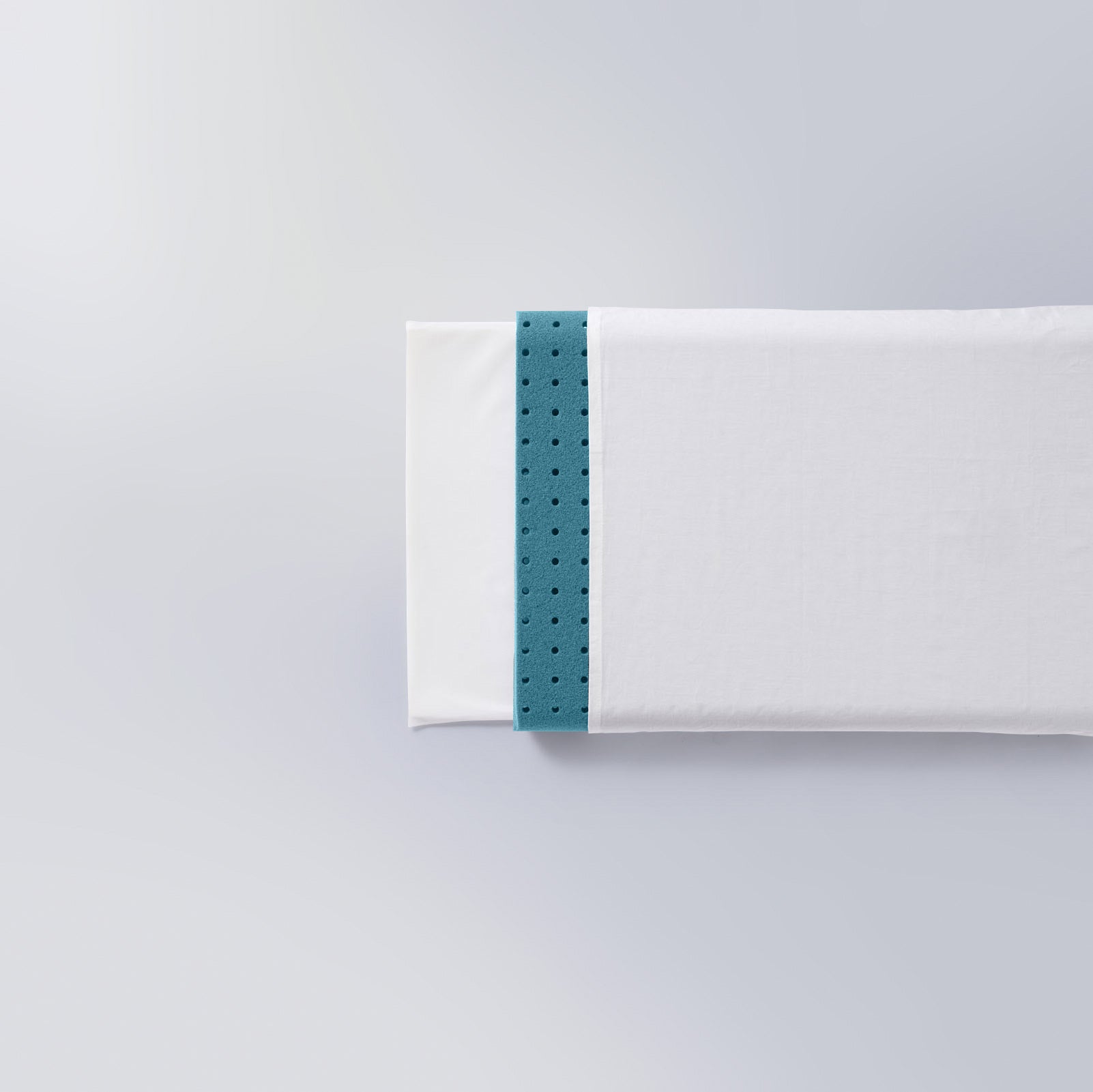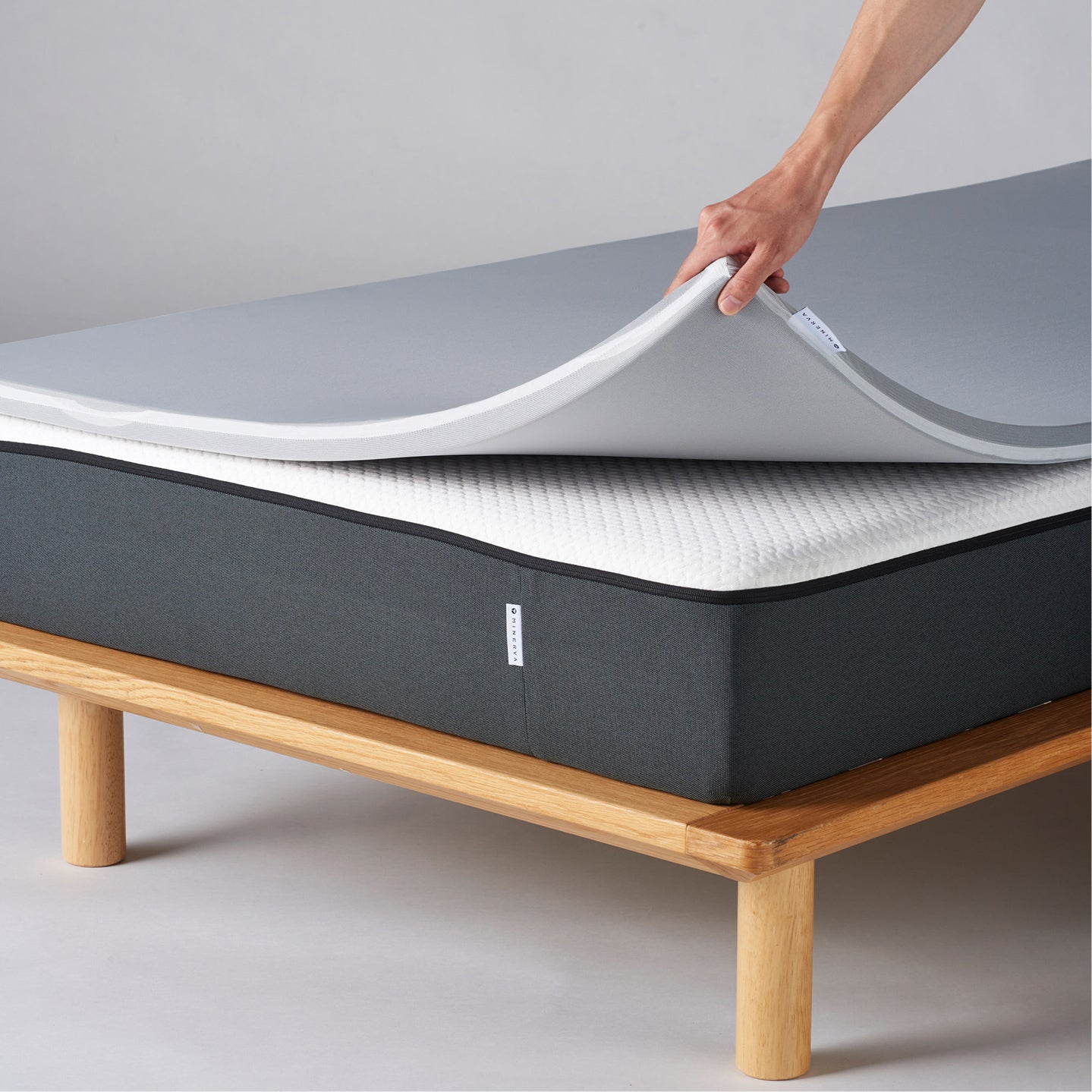マイカート
【いびき改善】枕で変わる!専門家が教える正しい選び方と科学的理由
Share

「いびきがうるさい」と、ご家族から指摘されたことはありませんか。ご自身では気づきにくいからこそ、どう対策すれば良いか悩みますよね。日中の眠気や倦怠感も、もしかしたら、いびきによる睡眠の質の低下が原因かもしれません。
この記事では、いびきが起こる原因から、枕で改善が期待できる科学的な理由まで分かりやすく解説します。さらに、枕選びで後悔しない4つのポイント、購入後に効果を最大化する使い方、そして枕と併せて実践したい生活習慣まで網羅的にご紹介。
あなたに最適な枕を見つけ、すっきりとした朝を取り戻しましょう。
いびきが起こる原因3選
いびきの正体は、狭くなった気道を空気が通る際の振動音です。つまり、何らかの理由で空気の通り道が狭くなっているサイン。
その原因は一つではなく、複数の要因が絡み合っていることがほとんどです。ここでは、いびきを引き起こす代表的な3つの原因を解説します。
合わない枕が引き起こす首の圧迫と気道の曲がり
毎晩使っている枕が、いびきの原因になっていることがあります。特に、枕の高さが体格に合っていないケースは少なくありません。
高すぎる枕は顎が引けて気道を圧迫し、低すぎる枕は頭が下がりすぎて気道を曲げてしまいます。気道は不自然に曲がることで空気の流れが妨げられるので注意が必要です。
体に合わない枕を使い続けることは、自ら気道を狭めていびきを誘発している状態と同じです。理想的な寝姿勢を保つ上で、枕の役割は非常に大きいといえます。
寝姿勢によって起こる舌の落ち込み
いびきの大きな原因の一つに、睡眠中の舌の落ち込みがあります。これは、特に仰向けで寝ているときに起こりやすい現象です。
仰向けで寝ると、重力の影響で舌の付け根部分である「舌根(ぜっこん)」が喉の奥へと沈み込み、気道を塞いでしまいます。これが、いびきが発生する仕組みです。飲酒や疲労で喉の筋肉が緩むと、舌はさらに落ち込みやすくなります。
特に、体重が増加傾向にある方は注意が必要です。首周りだけでなく舌自体にも脂肪がつくため、より重く、落ち込みやすくなります。横向き寝でいびきが軽減されるのは、この舌の落ち込みが物理的に起こりにくくなるためです。
仰向け寝が招く口呼吸と喉の乾燥・狭まり
仰向けで寝ていると、無意識のうちに口が開き、口呼吸になりがちです。実はこの口呼吸も、いびきを悪化させる一因となります。
本来、呼吸は鼻で行うのが自然な状態です。しかし、口呼吸では冷たく乾燥した空気が直接喉に当たり、粘膜を乾燥させてしまいます。
乾燥した喉は軽い炎症を起こしやすく、このわずかな腫れが気道をさらに狭め、いびきの音を大きくする原因になります。
朝起きたときに喉がイガイガする場合は、睡眠中に口呼吸になっている可能性が高いでしょう。枕の工夫で鼻呼吸を促すことも、いびき対策には重要です。
枕でいびきを改善できる科学的理由
枕はいびき改善において非常に重要な役割を果たします。
ここでは、枕がいびきを改善する科学的な理由を解説します。
枕で理想の寝姿勢を保ち気道を確保できるから
枕でいびきが改善できる最大の理由は、理想的な寝姿勢を保ち、気道をまっすぐ確保できるからです。
いびきは気道が狭まることで起こるため、最も重要な対策は「いかにして気道を広げるか」にあります。自分に合った枕は、マットレスと首の間にできる隙間を適切に埋め、立っているときと同じ自然な頸椎(けいつい)のカーブを維持してくれます。
この状態が、首周りの筋肉が最もリラックスし、かつ気道が広く確保された理想の寝姿勢です。合わない枕による気道の圧迫を、適切な枕で解消すること。これが、枕がいびき改善に効果的な科学的根拠なのです。
スムーズな寝返りを促し舌や口蓋垂の落ち込みを防ぐから
もう一つの理由は、適切な枕がスムーズな寝返りをサポートしてくれる点にあります。
人は一晩に20回以上も寝返りを打ちます。これには、同じ姿勢で眠り続けることによる体への負担を軽減するだけでなく、仰向け寝で落ち込んだ舌の位置をリセットする重要な役割があるのです。
しかし、枕が柔らかすぎると頭が沈み込んで寝返りが打ちにくくなってしまいます。逆に硬すぎたり、幅が狭すぎたりしても、スムーズな体の動きを妨げます。適度な反発力と十分な大きさのある枕は自然な寝返りを促し、舌の落ち込みが長時間続くのを防ぎます。
【失敗しない】いびきを改善する枕の正しい選び方4つのポイント
枕選びを誤ると、効果がないばかりか、首を痛めることにもなりかねません。そこで、枕選びで失敗しないための重要な4つのポイントを具体的に解説します。この基準に沿って選べば、あなたに最適な枕が見つかるはずです。
ポイント①「高さ」|気道を確保する最適な高さで選ぶ
枕選びで最も重要なのが高さです。理想的な高さとは、仰向けで寝たときに額から顎までのラインがやや下向き(約5度)になり、横向きでは首の骨と背骨が一直線になる高さです。
ご自宅で最適な高さを知る簡単な方法をご紹介します。壁を背にして、かかと・お尻・背中・後頭部を壁につけて自然に立ちます。このとき、壁と首の間にできる隙間の深さが、あなたに必要な枕の高さの目安です。
実際に枕を選ぶ際は、この目安を参考にしつつ、バスタオルを重ねて微調整しながら最も呼吸がしやすい高さを探してみてください。体格によって最適な高さは異なるため、客観的な基準を持つことが失敗しないコツです。
ポイント②「形状」|首のカーブを自然に支える形を選ぶ
次に重要なのが形状です。理想的な枕は、後頭部だけでなく、首のカーブをしっかりと支えてくれるものでなければなりません。
首の下に隙間ができてしまうと、その部分を支えようと首の筋肉が緊張し、リラックスできません。これでは気道の確保も妨げられます。そのため、首元が適度に盛り上がり、後頭部が収まる中央部分は少し低くなっている形状がおすすめです。
具体的には、首のカーブにフィットしやすいウェーブ型や、後頭部を優しく包み込むくぼみ型などが挙げられます。これらの形状は、仰向けでも横向きでも首を安定させやすく、気道を確保しやすいという利点があります。
ポイント③「素材」|寝心地とメンテナンス性で選ぶ
枕の素材は、寝心地の良さ、寝返りのしやすさ、そして手入れのしやすさに直結します。いびき改善のためには、適度な硬さと反発力があり、衛生的に使える素材を選びましょう。
柔らかすぎる素材は頭が沈み込みすぎて寝返りを妨げ、硬すぎる素材は首や頭に負担をかけます。また、枕は汗や皮脂で汚れやすいため、定期的にメンテナンスできるかも重要な選択基準です。
・高反発素材: 適度な反発力で寝返りをサポート。通気性が良く、洗えるものも多い。
・低反発ウレタンフォーム: フィット感は高いが、通気性が悪く洗えない製品が多い点に注意。
・パイプ素材: 通気性が抜群で丸洗い可能。高さ調整も自分でできるのが魅力。
それぞれの特徴を理解し、ご自身の好みやライフスタイルに合った素材を選んでください。
ポイント④「サイズ」|スムーズな寝返りのために十分な横幅を
意外と見落としがちなのが枕のサイズ、特に横幅です。寝返りを打ったときに頭が枕から落ちてしまうと、不自然な姿勢になり、いびきの原因となります。
安心して寝返りが打てるよう、枕には十分な横幅が必要です。目安としては、ご自身の頭3つ分の横幅、具体的には最低でも横幅60cm以上のサイズを選ぶことをおすすめします。
特に、体格が大きい方や、眠っている間によく動くと自覚している方は、通常より一回り大きいワイドサイズの枕を選ぶと安心です。窮屈さを感じさせない、余裕のあるサイズを選ぶことが、質の高い睡眠につながります。
【いびき改善を加速】枕の効果を最大化!購入後にやるべきこと
あなたにぴったりの枕を手に入れても、使い方が間違っていてはその効果は半減してしまいます。
ここでは、購入した枕のポテンシャルを100%引き出し、いびき改善効果を最大化するために、すぐに実践すべき正しい使い方とメンテナンス方法について解説します。
効果半減!やってはいけない枕の当て方と正しい使い方
枕の当て方一つで、気道の確保しやすさは大きく変わります。やってはいけないのは、枕に頭のてっぺんだけを乗せる当て方です。
この使い方では、首の下に大きな隙間ができてしまい、首が支えられません。結局、合わない枕を使っているのと同じように首が不自然な角度になり、気道を圧迫してしまいます。
正しい使い方は、枕を肩口までぐっと引き寄せ、首と枕の間に隙間ができないように深く頭を乗せることです。後頭部から首、そして肩の上部までが枕にしっかりと乗ることで、頸椎の自然なカーブが保たれ、気道がまっすぐに確保されます。
枕の寿命は?長持ちさせるメンテナンス方法と買い替えサイン
枕の寿命は、素材によりますが一般的に2〜3年が目安です。使い続けるうちに素材はへたり、本来の高さを保てなくなったり、反発力が失われたりします。へたった枕は体を正しく支えられず、再びいびきの原因となるのです。
枕を長持ちさせるには、定期的なメンテナンスが欠かせません。天気の良い日に陰干しして湿気を飛ばしたり、洗える素材であればこまめに洗濯したりして、清潔な状態を保ちましょう。
そして、「購入時より低くなった」「中央のへこみが戻らない」「朝、首や肩が痛い」といったサインが見られたら、それは枕の買い替え時です。
枕と併せて実践!いびきを根本から改善する生活習慣
いびき改善枕は非常に有効ですが、より根本的に悩みを解決するには、生活習慣の見直しも欠かせません。
肥満や飲酒、喫煙といった日々の暮らしの中に原因が潜んでいることも多いからです。枕による対策と並行して、これから紹介する生活習慣を実践し、相乗効果を狙いましょう。
寝酒は逆効果!アルコールがいびきを悪化させる理由
「寝つきを良くするため」と、就寝前にアルコールを飲む習慣は逆効果です。アルコールには全身の筋肉を弛緩させる作用があり、これには喉の周りや舌の筋肉も含まれます。
筋肉が緩むことで、通常よりも舌が喉の奥に落ち込みやすくなり、気道が狭くなります。普段はいびきをかかない人でも、お酒を飲んだ日に限っていびきをかくのはこのためです。
また、寝酒は眠りが浅くなり、睡眠の質を著しく低下させます。いびき改善のためには、少なくとも就寝の3〜4時間前には飲酒を終えるようにしましょう。
喫煙は喉の炎症のもと。禁煙がいびき改善への近道
喫煙習慣も、いびきと密接な関係があります。タバコの煙に含まれる有害物質は、気道の粘膜を直接刺激し、慢性的な炎症を引き起こします。
炎症によって喉や鼻の粘膜が腫れると、その分だけ空気の通り道は狭くなります。ただでさえ狭くなっている気道を無理に空気が通ろうとするため、いびきの音はより大きくなるのです。
いびきの改善はもちろん、ご自身の健康のためにも、禁煙に取り組むことは非常に大きなメリットがあります。まずは本数を減らすことから始めてみましょう。
首周りの脂肪が気道を圧迫。適正体重を目指す食事と運動
体重の増加、特に首周りについた脂肪は、物理的に気道を圧迫する直接的な原因となります。
太ると体の外側だけでなく、喉の内側にも脂肪がつきます。この内側の脂肪が気道を内側から狭めてしまうため、いびきが発生しやすくなるのです。
研究によれば、体重を5-10%減らすことでいびきの改善が期待できます。特に、大規模前向き研究では、10%の体重減少で睡眠時無呼吸指数(AHI)が26%改善することが示されています。
まずは、夕食の炭水化物を少し減らす、エレベーターを階段に変えるなど、食事と運動の両面からアプローチしましょう。
口呼吸を鼻呼吸へ。舌の落ち込みを防ぐ対策
睡眠中の口呼吸は、喉の乾燥や炎症を招き、いびきを悪化させます。これを防ぐためには、日頃から鼻呼吸を意識することが重要です。
鼻で呼吸すると、舌が自然と上顎の正しい位置に収まりやすくなり、喉の奥への落ち込みを防ぐ効果があります。まずは、日中の活動中から意識的に口を閉じ、鼻で呼吸する癖をつけましょう。
就寝中にどうしても口が開いてしまう場合は、薬局などで手に入る口閉じテープを試すのも有効な手段です。ただし、鼻詰まりがひどい場合は、まず耳鼻咽喉科を受診し、鼻の通りを良くする治療を優先してください。
まとめ
この記事では、いびきの原因から枕で改善できる理由、そして失敗しない枕の選び方や生活習慣の見直しまでを解説しました。
いびきの主な原因は気道の狭まりにあり、自分に合った枕で理想の寝姿勢を保つことが、その最も手軽で効果的な対策です。正しい枕選びの4つのポイントを参考に、あなたに最適な枕を見つけてください。
Share