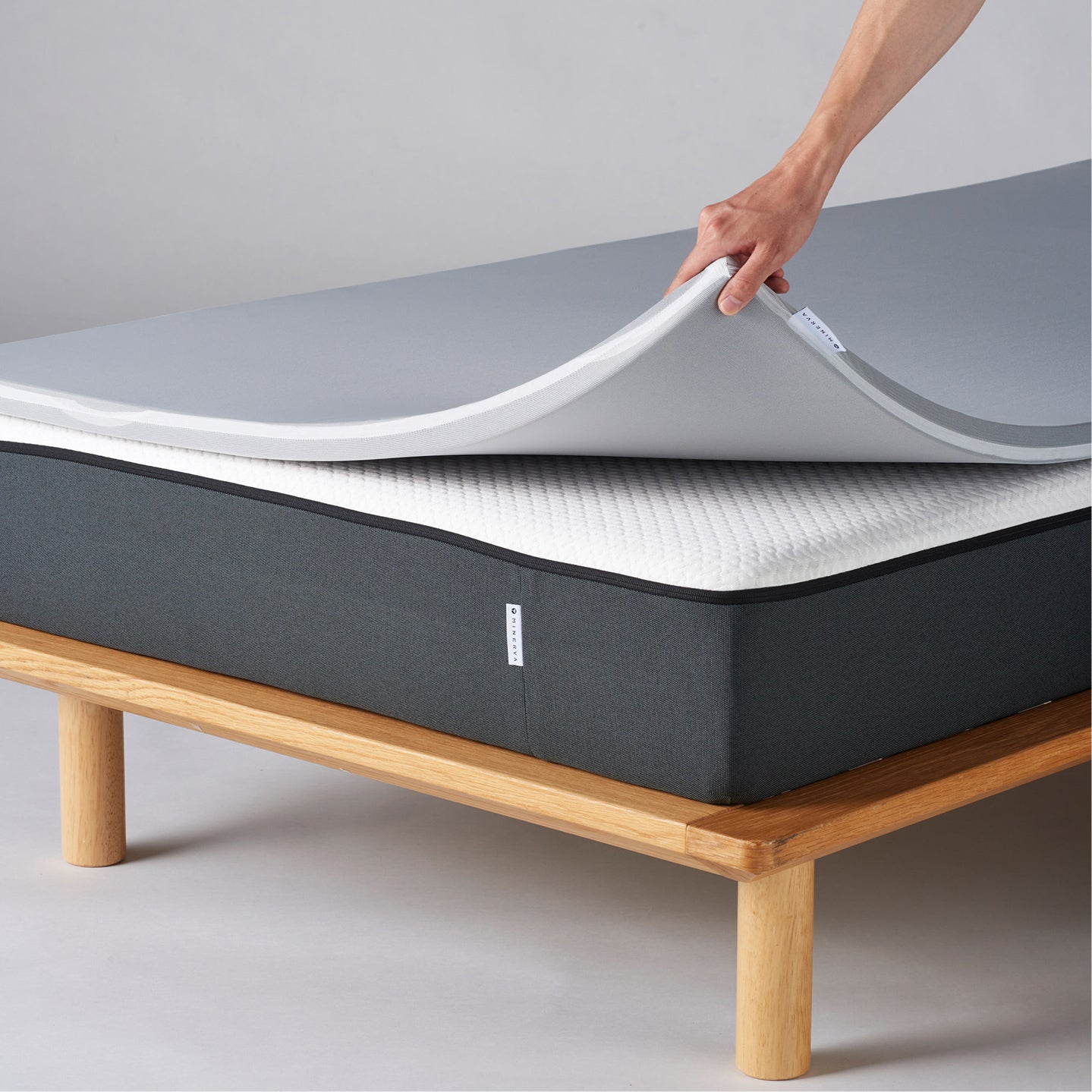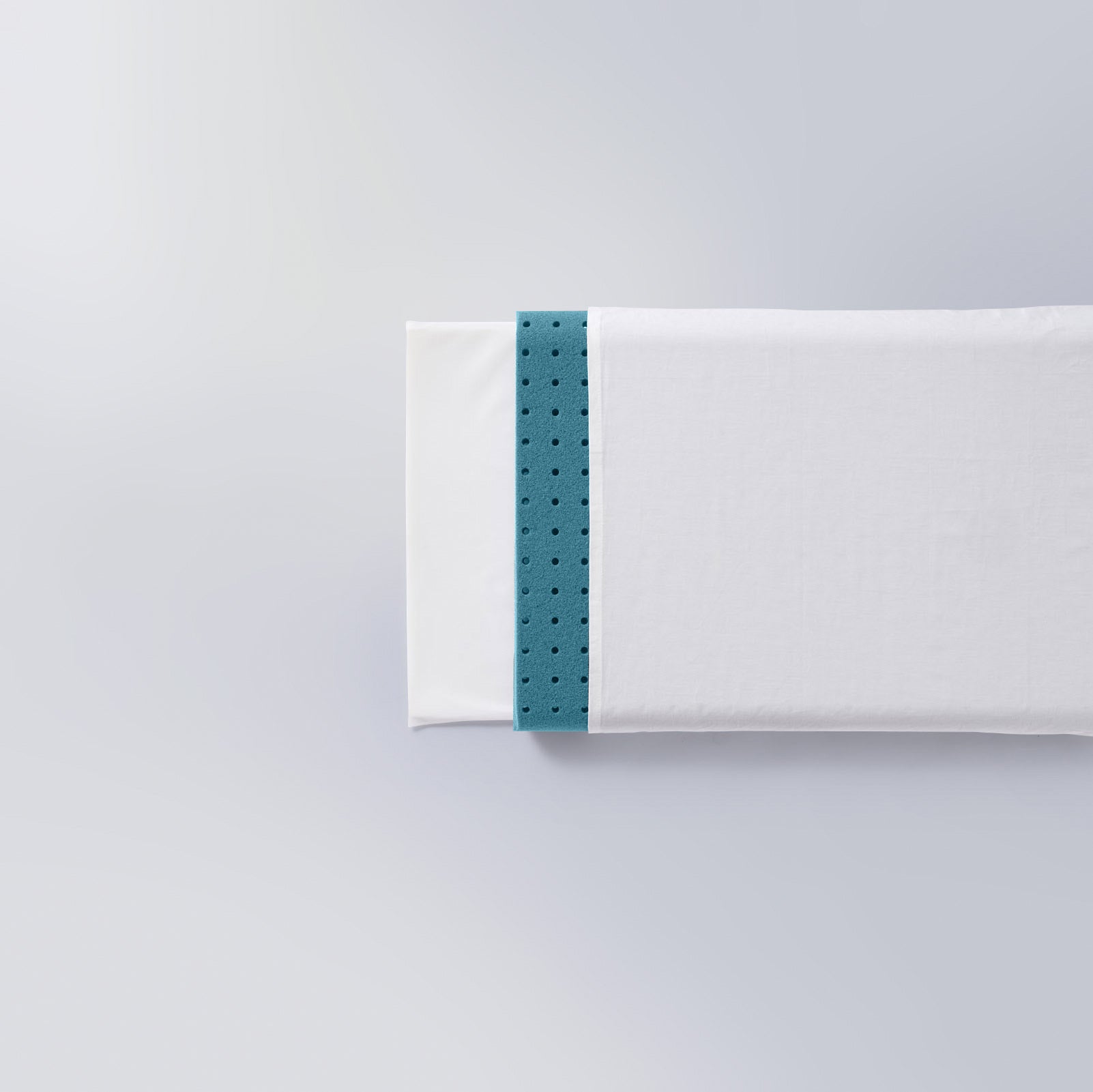マイカート
寝室の照明選びで快適空間を実現!おしゃれと快眠を両立させるコツを解説

「寝室の照明、なんとなく選んでいませんか?」
一日の終わりを過ごす大切な寝室。その照明一つで、睡眠の質も、部屋のおしゃれさも、心からのリラックス度も劇的に変わります。光は心と身体に深く影響するため、自分に合った照明を選ぶことが最高の癒やし空間を作る鍵なのです。
この記事では、快眠を導く「明るさ(ルーメン)」や「光の色(ケルビン)」といった基本の選び方から、複数の照明を組み合わせるだけでホテルのような上質な空間を演出するテクニックまで、誰でも実践できる具体的な方法を徹底解説します。
あなたに最適な照明を見つけて、毎日をリセットできる理想の寝室を手に入れましょう。
最高の睡眠環境は照明から|寝室の照明選びが重要な理由

寝室の照明は、ただ部屋を明るくするだけではありません。光は私たちの心と身体に深く関わっており、睡眠の質や日々の癒やしに大きな影響を与えます。
ここでは、寝室の照明選びが重要である2つの理由を具体的に解説します。
睡眠の質を左右する体内時計を整えるため
寝室の照明は、私たちの体内時計を整え、睡眠の質を高める上で非常に重要です。人間は、朝に強い光を浴びて目覚め、夜暗くなると自然に眠くなるリズムを持っています。
しかし夜に強い光を浴びると、脳が昼間だと勘違いしてしまい、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌が抑制されます。
その結果、寝つきが悪くなるなど睡眠の質が低下するのです。就寝前に適切な照明を選ぶことで、身体を自然と休息モードに切り替え、質の高い睡眠へと導きます。
心からリラックスできる癒やしの空間を作るため
寝室の照明は、一日の疲れを癒やすリラックス空間を作るために不可欠です。光の色や明るさは人の心理に大きく作用し、特に暖色系の優しい光には心を落ち着かせる効果が期待できます。
例えば、ホテルの部屋が心地よく感じられるのは、温かみのある間接照明などを巧みに使い、非日常的で落ち着いた雰囲気を演出しているからです。
日中の緊張から心と身体を解放するために、照明選びを工夫して心から安らげる癒やしの空間を寝室に作りましょう。
寝室の照明計画で最初に決めるべき2つの基本

快適な寝室作りは、照明の「明るさ」と「光の色」を決めることから始まります。
この2つの基本を押さえるだけで、寝室はただ眠るだけの場所から心と体を癒やす最高の空間に変わります。
自分に合った照明を選び、理想の睡眠環境を手に入れましょう。
「部屋の広さ」に合った明るさ(ルーメン)を選ぶ
寝室には、部屋の広さに適した明るさの照明を選びましょう。明るすぎると目が冴えてしまい、リラックスできません。逆に暗すぎても、本を読んだり作業をしたりする際に不便です。
照明の明るさは「ルーメン(lm)」という単位で表され、日本照明工業会が部屋の広さごとの推奨値を定めています。
以下の表を目安に、自分の寝室に最適な明るさを見つけてください。調光機能付きの照明なら、シーンに合わせて明るさを調整できるのでおすすめです。
|
部屋の広さ |
明るさの目安(ルーメン) |
|---|---|
|
~4.5畳 |
2,200~3,200 lm |
|
~6畳 |
2,700~3,700 lm |
|
~8畳 |
3,300~4,300 lm |
|
~10畳 |
3,900~4,900 lm |
|
~12畳 |
4,500~5,500 lm |
適切な明るさを選ぶことで、日中の活動モードから心身を自然にリラックスモードへと切り替えられます。
「光の色(ケルビン)」でリラックス効果を高める
リラックスできる寝室にするには、暖色系の温かみのある光の色を選ぶのがポイントです。光の色は「ケルビン(K)」という単位で示され、数値が低いほど暖色系、高いほど寒色系の光になります。
夕日のようなオレンジ色の光は、心身を落ち着かせて自然な眠りを誘う効果が期待できます。逆に、太陽光に近い白っぽい光は脳を活性化させるため、寝室のメイン照明には不向きといえるでしょう。光の色ごとの特徴を理解し、寝室にぴったりの色を選んでみてください。
|
光の色の種類 |
色温度(ケルビン)の目安 |
特徴・与える印象 |
|
電球色 |
約3,000 K |
温かみのあるオレンジ系の光で、リラックス効果が高い |
|
温白色 |
約3,500 K |
電球色と昼白色の中間で、落ち着きと自然さを両立 |
|
昼白色 |
約5,000 K |
太陽光に近い自然な光で、活動的な印象を与える |
|
昼光色 |
約6,500 K |
青みがかった最も明るい光で、集中力を高める |
就寝前は「電球色」の照明で過ごすことで、睡眠の質を高める準備が整います。
寝室をおしゃれにする照明の種類と特徴

寝室の照明と聞くと、部屋の真ん中にある丸いシーリングライトを思い浮かべるかもしれません。しかし、照明には様々な種類があり、それぞれに役割があります。
部屋全体を照らす「主照明」、癒やしの空間を作る「間接照明」、手元を照らす「補助照明」などです。
これらをうまく組み合わせることで、寝室はおしゃれで快適な空間に生まれ変わります。それぞれの特徴を知り、理想の寝室作りを始めましょう。
部屋全体を均一に照らす主照明(シーリングライト・ダウンライト)
主照明は、部屋全体を明るくする基本の灯りです。天井に直接取り付けるシーリングライトや、天井に埋め込むダウンライトがこれにあたります。
これらの照明は、部屋の隅々まで均一に光を届ける役割を持っており、掃除や着替え、部屋での探し物など、明るさが必要な活動をするときに欠かせません。
例えば、シーリングライトはデザインが豊富で、部屋のインテリアに合わせて選びやすいのが魅力です。一方、ダウンライトは天井をすっきりと見せられるため、モダンで開放的な空間を演出したい場合に適しています。
活動的な時間帯に必要な明るさを確保するために、まずは主照明の役割を理解しておきましょう。
空間に奥行きと癒やしを生む間接照明(フロアライト・ブラケットライト)
間接照明は、心からリラックスできる癒やしの空間作りに欠かせないアイテムです。光を壁や天井に一度当て、その反射した柔らかい光で周囲を照らすのが特徴です。
光源が直接目に入らないため眩しさを感じにくく、寝室に落ち着いた雰囲気をもたらします。
例えば、床に置くフロアライトを部屋の隅で使うと、光のグラデーションが生まれて空間に奥行きが生まれます。
また、壁に取り付けるブラケットライトは、ホテルのような上質でおしゃれな雰囲気を演出するのに最適です。就寝前のリラックスタイムは間接照明の灯りだけで過ごし、心と体を睡眠モードへと切り替えていきましょう。
読書や手元の作業に便利な補助照明(テーブルランプ・スポットライト)
補助照明は、読書やスマートフォンの操作など、特定の範囲だけを照らしたいときに活躍します。ベッドサイドに置くテーブルランプや、特定の場所を狙って照らせるスポットライトが代表的です。
これらの照明を使えば、部屋全体の明るさを落とした状態でも、手元はしっかりと明るく保てます。就寝時間が違うパートナーがいる場合でも、相手の眠りを妨げにくいというメリットがあります。
テーブルランプはコンセントに差すだけで手軽に導入でき、デザインも豊富です。補助照明を上手に取り入れることで、就寝前の時間をより快適で豊かなものにすることができます。
「シーリングライトはいらない」は本当?一室多灯の考え方
「寝室にシーリングライトはいらない」という話を聞いたことがあるかもしれません。これは、複数の照明を組み合わせて空間を演出する「一室多灯(いっしつたとう)」という考え方に基づいています。
部屋全体を1つの照明で照らすのではなく、フロアライトやテーブルランプなどをシーンに合わせて使い分ける方法です。
例えば、夜は天井の主照明を消し、間接照明と補助照明だけで過ごすことで、リラックス効果が格段に高まります。
このように光にメリハリをつけることで、部屋に立体感が生まれておしゃれな雰囲気を演出できます。
必ずしも主照明が不要なわけではありませんが、一室多灯を取り入れることで、ホテルのような上質な光の空間を実現してください。
【目的別】寝室でリラックスできる照明の使い方

おしゃれな照明を揃えても、使い方次第でリラックス効果は大きく変わります。
ここでは、就寝前から夜中まで、時間帯や目的に合わせた具体的な照明の活用法を3つ紹介します。
少しの工夫で、あなたの寝室が最高の癒やし空間に生まれ変わるでしょう。
就寝1〜2時間前は暖色系の間接照明で過ごす
就寝前の1〜2時間は、暖色系の間接照明だけで過ごすのがおすすめです。日中のような白い光は脳を活動的にさせますが、夕日のようなオレンジがかった光には心身をリラックスさせる効果があります。
この光が、自然な眠りを誘うホルモン「メラトニン」の分泌を促してくれるのです。寝室の主照明は消して、フロアライトやテーブルランプの柔らかい灯りだけで過ごしてみましょう。
照明を切り替える習慣は、心と体をスムーズに睡眠モードへ導くためのスイッチになります。
読書灯は目に優しく手元だけを照らす
ベッドでの読書には、手元だけをピンポイントで照らせる読書灯が最適です。部屋全体の照明をつけると、明るすぎて脳が覚醒してしまったり、隣で眠るパートナーを起こしてしまったりする可能性があります。
角度や明るさを細かく調整できるクリップライトやスポットライトなら、必要な範囲だけを照らせるので便利です。
光源が直接目に入らないよう、少し斜め上から本を照らすと目の負担も軽減できます。自分だけの光を確保し、周りを気にせず読書の世界に集中しましょう。
夜中に起きても睡眠を妨げないフットライトを活用する
夜中にトイレなどで起きる際は、足元を優しく照らすフットライトが役立ちます。天井の照明をつけてしまうと、強い光で目が冴えてしまい、再び寝付くのが難しくなることも少なくありません。
フットライトの低い位置からの淡い光であれば、脳への刺激を最小限に抑えつつ、安全な移動をサポートしてくれます。
人の動きを感知して自動で点灯するセンサー付きのタイプなら、スイッチを探す手間もありません。睡眠の質を維持しながら、夜中の安全性も確保しましょう。
ホテルのような寝室に|おしゃれな照明レイアウトのコツ

ホテルの客室は、なぜあんなにもリラックスできるのでしょうか?その秘密の一つが「照明の配置」にあります。
自宅の寝室も、いくつかのコツを押さえるだけで、まるでホテルのような上質でおしゃれな空間を演出可能です。
ここでは、今日から真似できる3つの照明レイアウト術をご紹介します。
光源を直接見せず眩しくないように配置する
おしゃれでリラックスできる空間作りの基本は、照明の光源(光を発する部分)が直接目に入らないようにすることです。
強い光が視界に入ると、人は無意識にストレスを感じてしまい、心からくつろぐことができません。
ホテルや高級レストランでは、光源を隠して光を壁や天井に反射させる「間接照明」が巧みに使われています。この手法で、空間全体が柔らかい光に包まれ、落ち着いた雰囲気になるのです。
具体的には、照明器具のシェード(傘)が電球をしっかり覆うデザインを選びましょう。また、天井を照らすフロアライトや、壁に光を当てるブラケットライトもおすすめです。
光源を見せない工夫一つで、光の質が格段に上がり、上質な癒やしの空間が生まれます。
照明を低い位置に置いて落ち着いた雰囲気を演出する
照明を床に近い低い位置に置くと、寝室全体が落ち着いた雰囲気に包まれます。人は視線が下がるほどリラックスしやすいと言われており、焚き火やキャンドルの光が心地よいのも同じ原理です。
天井から部屋全体を煌々と照らすのではなく、あえて低い位置に光を配置することで、空間の重心が下がって見え、心理的な安定感が生まれます。
例えば、ベッドサイドにテーブルランプを置いたり、部屋の隅にフロアライトを設置したりするのが効果的です。
就寝前の時間は天井の照明を消し、これらの低い位置の灯りだけで過ごしてみてください。天井に意識が向かなくなり、包み込まれるような安心感を得られるでしょう。
光と影のコントラストで部屋に立体感を出す
部屋の中に意図的に「光だまり」と「影」を作ると、単調になりがちな空間に立体感が生まれます。
寝室全体を一つの照明で均一に照らすと、のっぺりとした印象になってしまいます。
そこで、複数の照明を使って明るい場所と暗い場所のコントラスト(対比)を生み出すことで、部屋に奥行きと表情が生まれるのです。
これは「多灯分散」というプロも使うテクニックです。
例えば、壁に飾ったアートや観葉植物にスポットライトを当ててみましょう。照らされたモノが引き立ち、その周りに落ちる影が空間のアクセントになります。
また、フロアライトを壁際に置くだけでも美しい光のグラデーションができ、部屋が広く感じられる効果も期待できます。
【購入前に】寝室照明で後悔しないための3つのチェックポイント

デザインや機能で選んだ照明も、設置や日々の利用で問題があれば台無しです。
「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、購入前に必ず確認したい3つのポイントを解説します。
①設置場所の配線器具(シーリング)の種類を確認する
照明を購入する前に、まず天井の配線器具を確認しましょう。配線器具とは、照明を取り付けるためのコンセントのようなものです。
この部品の形状が照明器具と合わないと、残念ながら取り付けができません。賃貸物件でよく見る丸い形の「引掛シーリング」なら、工事不要で簡単に設置可能です。
しかし、古い物件などでは付いていない場合もあるため注意が必要です。天井の写真を撮っておくと、お店で相談する際にもスムーズになります。
購入前のひと手間で、設置できないといった最悪の事態を防ぐことが出来ます。
ベッドからのスイッチの操作性をシミュレーションする
ベッドに入ってから照明を消す手間を、一度想像してみてください。壁のスイッチまで移動するのは、意外と面倒に感じるものです。
特に冬の寒い日や疲れている日は、暖かいベッドから出たくないですよね。
そのため、ベッドに寝転んだ状態でスイッチを操作できるか、事前にシミュレーションしてみましょう。
もし壁のスイッチが遠いなら、リモコン付きの照明や、スマホで操作できるスマート照明を選ぶのが賢い選択です。日々の小さなストレスをなくすことが、快適な睡眠環境につながります。
掃除や電球交換のしやすさを見落とさない
照明の掃除や電球交換のしやすさは、見落としがちですが長く使う上で重要なポイントです。
照明に溜まったホコリは、部屋の明るさを損なうだけでなく衛生的にもよくありません。
例えば、布製で複雑なデザインのシェードは、掃除が大変になる可能性があります。また、照明の位置が高すぎたり重かったりすると、一人での電球交換は一苦労です。
自分の手で手軽にメンテナンスできるかという視点を持って選ぶことで、お気に入りの照明を長くきれいに使い続けられます。
まとめ|寝室の照明選びで理想の快眠空間を手に入れよう
寝室の照明は、ただ部屋を明るくするだけの道具ではありません。光の色や明るさを選ぶことで、心と身体のコンディションを整え、睡眠の質を劇的に向上させる力を持っています。
これまで何気なく使っていた天井の照明を、夜は少し暗めの間接照明に変えてみてください。それだけで、寝室は単なる「眠る場所」から「一日の疲れをリセットする特別な空間」へと生まれ変わるのです。
さらには、フロアライトやブラケットライトといった間接照明を上手に組み合わせ、落ち着いた雰囲気を演出してみましょう。
ぜひ、あなただけの理想的な快眠空間を実現してくださいね。
Share